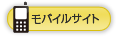国民年金について
国民年金は、老後の暮らしをはじめ、病気や事故で障害を負ったとき、家族の働き手がなくなったときなどに、みんなで暮らしを支えあうという社会保険の考え方で作られた仕組みです。
(参考:日本年金機構ホームページ)
・国民年金の種類
国民年金は20歳に到達すると、すべての国民が加入します。
加入者(被保険者)には以下の3つの種類があります。
1 第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満の自営業者、農家、学生、フリーターなど
保険料は自分で納めます。令和5年度は月額16,520円です。
2 第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合に加入している65歳未満の方
保険料は給料から天引きされます。
ただし、厚生年金や共済組合の加入者であっても、65歳以上の方で、老齢年金の受給権者は第2号被保険者とはなりません。
3 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
保険料を納める必要はありません。扶養している配偶者も保険料を納める必要はありません。
☆ 日本年金機構では、20歳を迎え、はじめて年金制度に加入する方に向けて特設ページを設けています。
動画による解説もありますので、以下のリンクからご覧ください。
(特設ページ)国民年金の加入と保険料のご案内
・国民年金第1号被保険者の資格取得手続きについて
60歳未満の方で、会社を退職した場合などは、役場または年金事務所で第1号被保険者の資格取得手続きが必要です。
また、第3号被保険者の方も、扶養から外れたり、扶養していた方が会社を退職したり65歳に到達したりした場合も同様に手続きが必要です。
必要書類は以下のとおりです。
(1)年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
(3)退職日や扶養から外れた日がわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、健康保険資格喪失証明書 等)
・保険料の納付方法
第1号被保険者の保険料は、次のいずれかの方法で納めることができます。
1 日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納める
2 口座振替
3 クレジットカード払い
2、3をご希望の場合は、申請が必要です。
以下の書類をご用意の上、役場住民課又は年金事務所でご相談ください。
(1)申請書 口座振替・・・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書
クレジットカード払い・・・国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
(2)年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
(3)口座振替・・・引落し用の通帳と通帳の届出印
クレジットカード払い・・・利用するクレジットカード
(4)国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(クレジットカード払いで、被保険者とカードの名義が異なる場合のみ)
・保険料の免除等制度について
所得が少ない、失業した等の理由で保険料を納めることが難しい場合、申請することで、保険料の免除等を受けられる場合があります。
1 免除・納付猶予制度
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一定以下の場合、その所得によって保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除されます。
本人が50歳未満で、本人と配偶者の所得が一定以下の場合、保険料の納付を猶予されます。
2 学生納付特例制度
20歳以上の学生について、本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
3 新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除
こちらをご覧ください。
4 災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難になった場合の特例免除
災害により被災し、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方が対象となります。
こちらをご覧ください。
※ 未納のままにしておくと、老後のための老齢基礎年金や、障害や死亡といった不慮の事態に障害基礎年金、遺族基礎年金などが受け取れなくなる可能性があります。
免除を受けることで、年金を受け取るための期間に算入させることができます。
役場住民課又は年金事務所で申請してください。必要書類は以下のとおりです。
(1)一般の方・・・国民年金保険料 免除・納付猶予申請書
学生の方・・・国民年金保険料 学生納付特例申請書
(2)年金手帳など基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカードなど個人番号がわかるもの
(3)学生の方・・・学生証または在学証明書 等
(4)失業を理由に申請する場合・・・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票 等の写し
(5)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・支給される年金額
令和5年度の国民年金の主な年金給付額は、以下のとおりです。
1 老齢基礎年金・・・795,000円
65歳から支給されます。金額は20歳から60歳に達するまでの40年間すべての期間を納付した場合のものです。
なお、何かの事情で保険料を納付することができなかった期間がある人については、その期間分だけ年金額が減額されます。
2 障害基礎年金・・・1級 993,750円
2級 795,000円
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
3 遺族基礎年金・・・795,000円
亡くなった方に生計を維持されていた、子のある配偶者または子が受け取れます。
(子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子をいいます。)
※ 上記は年金額の例です。加入期間や納付期間、免除月数、世帯の状況等によって年金額が変動します。また、未納期間が長いと受け取れない場合があります。
・年金受給に必要な書類等
年金を受けることができるようになった場合は、その年金の種類や、加入していた年金の制度等によって、必要書類や提出先が異なります。
詳しくは役場住民課またはお近くの年金事務所でご相談いただくか、日本年金機構ホームページをご覧ください。
・その他
国民年金保険料や年金受給についての各種ご相談でご来庁の際は、以下の書類をご用意ください。
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証 等)
(2)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、年金証書、年金振込通知書 等)
(3)年金を受給中の方・・・受給中の年金の種類がわかる書類(年金証書、年金振込通知書 等)
(4)ご本人が来庁できない場合・・・委任状(記入例)と委任者・来庁者の本人確認書類
〇日本年金機構ホームページ
〇住民課国保年金係へのメールでのお問い合わせはこちらから