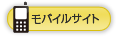国民健康保険について
国民健康保険(国保)は、私たちが病気やケガをしたときに安心して医療を受けられるよう、普段からお金(保険税)を出し合い、みんなで支え合って、個々の経済的負担を軽くすることを目的としています。
【国民健康保険の加入・脱退の手続きについて】
社会保険や後期高齢者医療などに加入していない方は、国民健康保険の加入の手続きが必要です。
また、国民健康保険に加入している方が社会保険に入る場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要となります。
加入・脱退の手続きが必要な場合と、その際に必要な書類をご案内します。
本人確認書類(※)をお持ちの上、役場住民課でお手続ください。
郵送でのお手続の場合は、様式をダウンロードいただき、本人確認書類(※)の写しを添付の上、
役場住民課国保年金係(038-1113 田舎館村大字田舎舘字中辻123-1)宛てに送付してください。
マイナンバーを記入した場合は、マイナンバーがわかる書類(※2)も提示してください。(郵送の場合は、写しを添付)
☆☆☆国民健康保険の手続きのオンライン申請を開始しました☆☆☆
国保の一部手続きが、マイナンバーカードを使用してオンラインでできるようになりました。
オンラインでの手続きについては、こちらを御覧ください。
| ※ 本人確認書類は次のいずれかです。 | |
| 1つでよいもの | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポートなど(顔写真付きで官公庁が発行したもの) |
| 2つ必要なもの | 資格確認書(保険証)、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、その他顔写真のない官公庁が発行した書類など |
| ※2 マイナンバーがわかる書類 | マイナンバーカード(両面)、マイナンバー付き住民票、マイナンバー通知カード(通知カードの場合は、記載されている住所が住民票上の住所と同じ場合に限ります。) |
| 種類 | 届け出が必要なとき | 添付書類 |
|---|---|---|
| 加入 |
他の市町村から転入 |
転出証明書 |
| 他の健康保険(社会保険など)を脱退 |
(1) 国民健康保険・国民年金異動届出書
(2) 社会保険等の資格喪失証明書 社会保険脱退の事実や日付、扶養親族等の情報について 証明するものです。 事業所に記入・押印してもらう必要があります。 必要事項が記入されていれば、事業所の独自様式でも構いません。 協会けんぽからの脱退した場合、 年金事務所で証明可能な場合もあります。 |
|
| 生活保護を受けなくなった | 保護廃止決定通知書 | |
| 出生 |
出生を確認できるもの (出生証明書・母子健康手帳など) |
|
| 脱退 | 他の市町村に転出 | 資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証) |
| 他の健康保険(社会保険など)に加入 |
(1) 国民健康保険・国民年金異動届出書
(2) 新しく加入した社会保険の保険証、資格情報のお知らせ、 資格確認書、マイナポータルで表示した健康保険の資格情報画面 ※ 資格情報のお知らせや資格確認書が届くのに時間がかかる場合は、 社会保険等の資格取得証明書でも替えられます。
※ これまで使っていた国保の各種証は、ご自身で裁断・破棄 していただくか、窓口で回収します。 |
|
| 生活保護を受け始めた | 保護開始決定通知書、資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証) | |
| 死亡 |
(1)亡くなった方の資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証) (2)喪主の通帳 または 公金受取口座を利用する場合はマイナンバーカード (3)喪主のマイナンバーがわかる書類 |
|
| その他 | 退職者医療制度に該当・非該当 | 年金証書、資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証) |
| 住所・世帯主・氏名が変わった | 資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証) | |
| 就学で他の市町村に住む |
(1)在学証明書 (2)資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証) (3)学生と世帯主のマイナンバーがわかる書類 |
|
|
保険証を紛失 |
被保者証等再交付申請書.xlsx(48KB) |
【マイナ保険証への移行について】
令和6年12月2日をもって、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証として登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用を基本とする制度に移行しました。
移行後以降に国保に加入した場合は、保険証は発行されませんので、マイナ保険証を登録済みの方は、マイナ保険証を利用して受診してください。
(マイナ保険証を登録していない場合は、保険証に代わる資格確認書が交付されます。)
なお、令和6年12月1日以前に発行された田舎館村国保の保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。(途中で70歳、75歳到達する方を除く)
有効期限が到来するまでの間は、保険証も使うことができます。
なお、マイナ保険証に移行後も、就職や退職の際の国保・社保の切り替えの手続きは必要ですので、
上の【国民健康保険の加入・脱退の手続きについて】をご確認いただき、お手続ください。
【国保の手続きをする前に】
同世帯に社会保険に加入している家族がいる場合、社会保険の扶養になれるかどうかの確認をしてください。
社会保険の被扶養者となった場合は、被扶養者の健康保険料や国民健康保険税は課税されません。
また、社会保険では被扶養者が増えても、加入者の給料から差し引かれる保険料は変わりません。
被扶養者として認められるには親族関係や収入などの条件がありますので、
詳しくは、お勤めの事業所にご確認ください。
【国民健康保険税について】
国民健康保険税については、こちらのページをご覧ください。
【国民健康保険の給付】
-
自己負担割合
-
1)医療費の自己負担割合
入院
通院
未就学児
2割
2割
一般被保険者
3割
3割
退職者被保険者等(本人)
3割
3割
退職者被保険者等(被扶養者)
3割
3割
70歳以上(一般)
2割
2割
70歳以上(現役並み所得者)
3割
3割
-
2)入院中の食事代の自己負担割合(標準負担額)
一般の被保険者
1食460円
住民税非課税世帯等の人
90日までの入院
1食210円
90日を超える長期入院の場合
1食160円
所得が一定の基準に満たない70歳以上の方
1食100円
-
-
高齢受給者証の交付について
-
70歳を迎えた方には、被保険者証と一体化された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から負担割合が変更になります。
-
-
-
妊産婦
-
医療費の自己負担割合
妊産婦
自己負担なし(10割給付)
通院のみ
-
【出産育児一時金(原則50万円)の支給】
被保険者が出産したときには出産育児一時金(原則50万円)を支給します。
-
産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は、48万8千円になります。
-
直接支払制度
-
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として国保から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになっています。原則50万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなっています。
-
-
出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を国保に請求することができますので、お問い合わせください。
-
出産育児一時金が国保から病院などに直接支払われることを望まない場合は、出産後に国保から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。ただし、この場合は、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。
【葬祭費(5万円)の支給】
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人(喪主)に葬祭費(5万円)を支給します。
<申請に必要なもの>
1.亡くなった方の資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証)
2.喪主の本人確認書類
3.喪主のマイナンバーがわかる書類
(マイナンバーカード(両面)、マイナンバー付き住民票、マイナンバー通知カード(ただし、記載されている住所が住民票上の住所と同じ場合に限ります。))
4.葬祭費支給申請書.pdf(83KB) ※受付窓口(役場1階住民課国保年金係)にも用意しています。
5.喪主名義の通帳 または 公金受取口座を利用する場合はマイナンバーカード
(喪主以外の方が受け取る場合、申請書の委任欄に喪主の署名または記名押印が必要です。)
☆☆☆葬祭費の支給申請手続きのオンライン申請を開始しました☆☆☆
マイナンバーカードを使用してオンラインでできるようになりました。
オンラインでの手続きについては、こちらを御覧ください。
【療養費】
補装具(コルセット等)代など一旦全額自己負担した場合は、申請し審査で決定すると自己負担分を除いた額が支給されます。
<申請に必要なもの>
1.マイナンバーカード または 資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証)
2.「世帯主」と「療養を受けた方」のマイナンバーがわかる書類
(マイナンバーカード(両面)、マイナンバー付き住民票、マイナンバー通知カード(ただし、記載されている住所が住民票上の住所と同じ場合に限ります。))
3.療養費支給申請書.pdf(107KB) ※受付窓口(役場1階住民課国保年金係)にも用意しています。
4.領収書
5.医師の診断書
6.世帯主名義の通帳 または 公金受取口座を利用する場合はマイナンバーカード
(世帯主以外の方が受け取る場合、申請書の委任欄に世帯主の署名または記名押印が必要です。)
【柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方】
柔道整復師とは、骨折・ねんざ・打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。柔道整復師による施術は、保険証が使える場合と、そうでない場合があります。
施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けましょう。
柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方.pdf(329KB) 柔道整復_適正化パンフレット.pdf(70KB)
【海外療養費】
海外旅行中などに急病やケガなどで病院にかかった場合、その費用について全額を現地で支払ったうえで、後日、国保給付係へ申請していただくことで、国保で認められた部分を支給します。
帰国後、必要書類を確認の上、窓口にて申請してください。郵送での申請はできません。
<申請に必要なもの>
1.マイナンバーカード または 資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証)
2.「世帯主」と「療養を受けた方」のマイナンバーがわかる書類
4.診療内容明細書.pdf(82KB)(診療内容明細書と領収明細書は原則、診療を行った医師や、病院の会計担当の方が作成するものです。 医療機関で月ごと、入院・外来別で作成していただく必要があります。)
5.領収明細書.pdf(63KB)(領収明細書と実際の領収書の金額に差異がある場合には、審査ができません。 必ず金額が一致していることを確認した上で、ご申請ください。)
6.現地医療機関が発行した領収書等の書類(原本と日本語訳。審査の厳格化に伴い、現地医療機関の書類につきましては、全て日本語訳が必要です。)
7.パスポート等(パスポートが用意できなければ、航空券など出・入国がわかるもの)
8.調査に関わる同意書(海外療養費).pdf(66KB)(申請時に窓口で記入していただきます。)
9.世帯主の日本国内の口座の通帳 または 公金受取口座を利用する場合はマイナンバーカード
(世帯主以外の方が受け取る場合、申請書の委任欄に世帯主の署名または記名押印が必要です。)
<海外療養費の支給対象とはならない場合>
(1)治療を目的に海外へ渡航し、治療を受けた場合
(2)治療が日本国内の保険診療として認められていない場合
例えば、次のようなものです。
・保険のきかない診療、差額ベッド代
・美容整形
・高価な歯科材料を使ったとき、歯列矯正
・交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気やケガ
※注意事項※
・海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で受診した場合の費用を基準として計算し、実際に海外でかかった費用を日本円に換算した金額と比較して、低い方の金額を支給します。
・診療を受けた日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができません。ご注意ください。
・書類不備の場合は支給ができない場合がありますので、記入後の書類を確認したうえで申請してください。
・海外旅行に行く際は、民間の旅行保険に加入することをお勧めします。
・不正請求に対しては、警察と相談・連携して厳正な対応をとっています。昨今の海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっている事情から厚生労働省、警察庁の指導の元、審査の強化を行うことになっています。渡航の確認や翻訳文の確認等を行う場合があるため、支給の決定まで大変長い期間がかかることがあります。
【限度額適用認定証】
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することにより、1つの医療機関でのひと月の支払額は、自己負担限度額までとなります。
ひと月の限度額は、世帯の所得や、かかった医療費に応じて異なります。
申請することで発行することができます。
★ なお、マイナ保険証で受診すると、
限度額の情報を医療機関がオンラインで確認できるため、
限度額認定証を提示しなくても限度額が適用されます。
役場での限度額認定証の申請が不要となりますので、マイナ保険証の利用を御検討ください。
(詳しくはこちら) 限度額適用認定証について.pdf(102KB)
※ 限度額が適用されるのは、保険適用の診療に限ります。
保険外診療や、食事代、ベッド代、診断書作成などは別途お支払いいただく必要がありますのでご注意ください。
<申請に必要なもの>
1 マイナンバーカード または 資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証)
※ 限度額適用認定証は、毎年7月31日が有効期限です。更新には申請が必要ですので、
マイナンバーカード または 資格情報のお知らせ または 資格確認書(保険証)をお持ちください。
※ 70歳以上の方は、世帯所得により限度額認定証が発行されない場合がありますので、
事前にお問い合わせください。
※ マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても限度額が適用されるため、申請不要です。
【高額療養費(医療費が高額になったとき)】
〇高額療養費
同じ月内に支払った医療費(保険適用分に限る)が限度額を超えたとき、申請すると超えた分が払い戻しされる制度です。
(役場窓口で申請する場合)
<申請に必要なもの>
1.世帯主の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)
2.世帯主の保険証または資格確認書
3.高額療養費支給簡素化申出書兼同意書.pdf(169KB) ※受付窓口(役場1階住民課国保年金係)にも用意しています。
4.世帯主名義の通帳 または 公金受取口座を利用する場合はマイナンバーカード
(世帯主以外の方が受け取る場合、申請書の委任欄に世帯主の署名または記名押印が必要です。)
※ 令和6年8月以前の診療分は、医療費等の領収書が必要です。
☆☆☆高額療養費申請の手続きのオンライン申請を開始しました☆☆☆
令和6年9月以降診療の高額療養費について、
マイナンバーカードを使用してオンラインでできるようになりました。
オンラインでの手続きについては、こちらを御覧ください。
〇高額療養費貸付事業
高額療養費の払い戻しをうけるには、診療月から3か月以上後になります。
そのため、当面の高額療養費の支払いに充てる資金として、
無利息で高額療養費支給見込額の9割相当額の貸付を行う
「高額療養費貸付事業」を実施しています。
(注)これから高額な診療を受ける方は「限度額適用認定証」をご利用ください。
<申請に必要なもの>
1.保険証
2.世帯主名義の通帳(世帯主以外の口座に振込を希望する場合は委任状が必要です。)
3.医療機関などからの請求書
(注1)4~6は受付窓口(役場1階住民課国保年金係)にも用意しています。
(注2)5は事前に医療機関などで手続きが必要です。
【国民健康保険の第三者行為について】
〇第三者行為とは
交通事故や暴力行為等で、第三者(加害者)の行為により負傷した場合が「第三者行為」にあたります。
〇手続きの流れ
-
国保で受診する場合は、役場住民課国保年金係に連絡する。
-
役場住民課国保年金係に、以下の<第三者行為の届出に必要なもの>にある書類を提出する。
(事故等の内容により、<第三者行為の届出に必要なもの>以外の書類の提出をお願いする場合があります。)
※ 緊急の場合は、受診後にできるだけすみやかに提出をお願いします。
※ 交通事故の場合は、必ず警察にお届けください。
〇国保で使って治療を受けられない場合
-
負傷された自身に、法令違反や重大な過失(飲酒・喧嘩等)がある場合。
-
通勤中や業務中の事故等、労災が適用される場合。
-
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず役場住民課国保年金係にご相談ください。
〇医療費の負担者~
医療費は、原則として加害者が支払うべきものですが、国保が一時的に医療費を立て替えたあと、加害者(損害保険等)に請求することになります。
<第三者行為の届出に必要なもの>
覚書統一様式
- 第三者行為による傷病届.pdf(97KB) エクセル版第三者行為による傷病届.xlsx(93KB)
- 事故発生状況報告書.pdf(120KB) エクセル版事故発生状況報告書.xlsx(34KB)
- 同意書.pdf(77KB) エクセル版同意書.xlsx(17KB)
- 交通事故証明書(※警察に届け出し、交付をうけてください。事故証明書を提出できない場合は、下の入手不能理由書を提出してください。)
- 交通事故証明書入手不能理由書.pdf(52KB) エクセル版交通事故証明書入手不能理由書.xlsx(34KB)
(国保連様式)
〇住民課国保年金係へのメールでのお問い合わせはこちらから